現代の日本の警察の基礎はフランスに倣って作られたものだそうだ。私はこれを司馬遼太郎さんの『翔ぶが如く』を読んで知った。初代大警視となった川路利良はフランスに視察に行った際、大切なカバンを無くしてしまった。もう見つかるまいと思っていたが、警察から連絡があって行ってみるとカバンが届けられていた。中身を確かめるよう言われて見てみると、何も無くなっていなかった。日本ではあり得ない!と川路はすっかり感心し、これから作られる日本の警察もこうでなくてはならないと思った…確かこんな話だったと思う。現代の私たちにとっては、この話は何重にも驚きである。当時は日本よりフランスの方が治安が良かったのか!今日本の観光客がパリに行ってカメラを置き忘れたら、絶対に戻って来ないという印象がある。(実際にはそれほどではないのだけど)もう一つの驚きは、戦前戦中の恐ろしい警察のイメージとあまりにも違うことである。とはいえ、『火垂るの墓』(アニメ版)に出て来る警察官は、飢えのあまり畑の作物を盗んだ少年に思いやりを見せている。また、赤塚不二夫さんが子どもの頃、お父さんは満州で警察官をしていたと聞いたことがあるが、赤塚さんの初期の漫画には優しいお巡りさんが出て来る。ということは、特高警察と一般の警察官は違うものだったということか。それとも、優しいお巡りさんに別の顔があったのか。いずれにせよ、「日本警察の父」の頭に最初に宿ったコンセプトは、市民に近いところで市民に奉仕する警察だったらしい。それはまさに、私の幼い日の思い出の交番と重なる。 冒頭の写真はパリの騎馬警官。フランスでは今でも警官が馬に乗って業務に当たることがある。
<スポンサーリンク>
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISH 
銃の発砲事件は日本では珍しい。
しかも凶器は交番の警官を殺害して盗んだものだった…
まるでどこか他所の国で起きた事件みたい。
だが、日本だから起きた事件だとも言える。
どこの国にでも交番と言うものがあり、おまわりさんが道を教えてくれるなどと思ってはいけない。
そして日本の交番には、誰もが入って行くことができる。
幼い頃、友達と遊んでいて十円玉を一つ拾った。
「十円玉だ。どうする?」
「道に落ちてるものは交番に届けるんだよ。」
「だよね。」
というわけで、私は誰かの大切な10円玉を握りしめ、友達と一緒に駅前の交番まで行った。
すると若いお巡りさんは同僚と相談し、私たちに真面目な顔で5円づつくれた。
今思うと、彼らのポケットマネーだったに違いない。
将来の良き市民はこうして、落ちているものは正直に交番に届けるのだということを学んだ。
あの日突然刃物で襲われた警察官も、こんなお巡りさんだったかもしれない。
拳銃で襲われた小学校の警備員も、 こんな警備員さんだったかもしれない。
<スポンサーリンク>
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISH 
 西洋は個人主義だと言われる。
個人主義という言葉が何を意味しているかは難しい。
というか使われ方が曖昧で、フランスですらいい加減に使っている人が多いという印象だ。
いずれにせよ、個人主義だからチームワークがないということにはならない。
チームワークというものは、それなりにどんな文化にもある。
人類が協力して大自然の中で暮らしていた、原始の時に始まったものなのだから。
個人主義の観点からチームワークを見れば、チームとは独立した個人が連携して仕事をするということになるのだろう。
一方、個人主義でない場合というのは、集団が先にあるということになるのか。
だとすれば、個人は集団に依存する「部分」だから、その集団を離れて個人のみでは動けないということになる。
つまり、自分が所属している集団の中では力を発揮できるが、その外に出た時に他者と繋がることはできないということだ。
もちろん、西洋が100%個人主義でアジアが100%集団主義(?)だなどということはあり得ない。
ただ、「連帯」が「団結」とも「助け合い」とも違う理由はここにあるのかもしれない。
個人主義が人間を信じるとすれば、集団主義は自分の集団のみを信じる。
人間を信用していなければ、自分と自分の集団(家族や国家)だけを守ろうとするのは当たり前だ。
だから、人間を信頼することがなければ、「連帯」はありえない。
<スポンサーリンク>
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISH
西洋は個人主義だと言われる。
個人主義という言葉が何を意味しているかは難しい。
というか使われ方が曖昧で、フランスですらいい加減に使っている人が多いという印象だ。
いずれにせよ、個人主義だからチームワークがないということにはならない。
チームワークというものは、それなりにどんな文化にもある。
人類が協力して大自然の中で暮らしていた、原始の時に始まったものなのだから。
個人主義の観点からチームワークを見れば、チームとは独立した個人が連携して仕事をするということになるのだろう。
一方、個人主義でない場合というのは、集団が先にあるということになるのか。
だとすれば、個人は集団に依存する「部分」だから、その集団を離れて個人のみでは動けないということになる。
つまり、自分が所属している集団の中では力を発揮できるが、その外に出た時に他者と繋がることはできないということだ。
もちろん、西洋が100%個人主義でアジアが100%集団主義(?)だなどということはあり得ない。
ただ、「連帯」が「団結」とも「助け合い」とも違う理由はここにあるのかもしれない。
個人主義が人間を信じるとすれば、集団主義は自分の集団のみを信じる。
人間を信用していなければ、自分と自分の集団(家族や国家)だけを守ろうとするのは当たり前だ。
だから、人間を信頼することがなければ、「連帯」はありえない。
<スポンサーリンク>
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISH 
ワールドカップの初戦で日本がコロンビアに勝つという快挙を成し遂げ、渋谷に集まっていた人々は沸き返った。普段、東京では知らない者同士が声を掛け合うということは少ない。「サッカー」という共通項で、見知らぬ人々が喜びを共にした。これもスポーツの効用にちがいない。普段の生活に戻れば、日本人が知らない者同士で声を掛けにくくなったのはいつからだろう。都市部と小さな町、村でも違いがある。ある若いフランス人の女の子が東京で生活した時の話だ。彼女は東京が好きだったが、人と人との関係が疎遠だとも感じていた。ある日、駅で転んでしまった。大したケガをしたわけでもないが、とても寂しくなってしまったと言う。誰も声を掛けてくれなかったからだ。休暇でパリに戻った時、階段でちょっと躓いたら、周りから一斉に「大丈夫ですか。」と言われて安心したとか。私も、パリで始終同じような光景を目にした。パリのメトロでベビーカーを使っていた時は、いつも他の乗客に手伝ってもらったものだ。フランスはドイツほどバリアフリーが進んでいない。日本人はシャイだから、大ごとでない限り声を掛けられないのだろうか。大災害でも発生しない限り、私たちは「助け合いの精神」を発揮できないのだろうか。しかし、それでは説明がつかない。十年以上前に、若い男性が駅のホームで死ぬまで殴られるという事件があったのを覚えているだろうか。混み合う時間帯でホームに人が溢れていたのに、誰も関わり合いになろうとしなかったという事件である。その時犯人は、銃もナタも持ってはいなかった。自分のすぐ近くで一人の人が殺されていくのに、反応しない群衆。私たちの社会は一体どうなってしまったのだろうと戦慄した人は少なくなかったのではないか。
<スポンサーリンク>
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISH 
(前回よりの続き)新幹線殺傷事件を知って私が思い出した出来事とは、次のようなものだった。知人のフランス人が東京を旅行していた時、ある駅の近くで一人の男が通りがかりの人たちに暴力を振るっているのを見た。お年寄りや子どもを殴り、子どもは泣き出したと言う。そのフランス人は日本語はあまりできないのだが、その男の肩を掴むと壁に押し付けた。すると幸いなことに、男は大人しくなった。ところで、その時フランス人が驚いていたのは事件そのものより周りの人の反応だったという。 他にも大勢人は通ったのだが、誰も介入しなかった。むしろ関わり合いになるのを避けているようだった。自分が男に働きかけた時も、誰も加勢に来なかったというのである。それは、今回新幹線の中で起こった凶悪事件とは比べものにならない、些細な出来事であった。今回のように相手が素手ではなく、ナタを振り回している時に何ができるだろう。それでも亡くなった梅田さんは、不断の信念に基づいて、恐らくとっさに行動したのではないか。女性が一人で殺されてしまった、誰も助けようとせずに、という結末にはならなかった。関わり合いになった人がいたから。そしてその人は犠牲になってしまった。 一人で。
<スポンサーリンク>
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISH 
フランス語や英語でよく使われる言葉で日本人があまり使わないものの一つに、「連帯」がある。
日本語で連帯と言うと左翼活動家みたいになってしまうのだが、フランスなどでは政治的な意味に限らず色々な場面で使われる言葉だ。
「連帯」、英語でsolidarityフランス語でsolidarite (最後のeの上には何か付きますが、文字化けする恐れがあるのでここでは省きます)。
日本語では「団結」と訳されることも多いが、「団結」では合わないことも多い。
日本語で強いて説明すれば、困っている人への共感とか、窮地に陥った人の立場に立って、自分のこととして考え、行動しようとする意識と言えるだろう。
日常的な場面で使われる場合は、「助け合いの精神」が近い。
だが、「助け合い」では困ることもある。
例えば、難民を受け入れる時やテロが起こった時だ。
「テロの犠牲者とのsolidarite」を訳そうとすると、助け合いでもおかしいし団結も違う。
最近よく使われる「つながる」 という動詞が合っている。
なぜこんな話を長々とするかというと、フランス人の知人が東京を訪れた時の出来事を思い出したからだ。
新幹線で突然男がナタを振り回し、 切りつけられた女性を助けようと立ち向かった男性が一人で殺されてしまったというニュースを聞いた時に。
(つづく)
<スポンサーリンク>
業界初・オンライン特化型コーチ スタディサプリENGLISH

PMIは、いわばフランスの子育て支援センター。PMI - Protection Maternelle et Infanile母子保護という意味で父親という言葉は入っていないのだが、1945年に設立された当時、イクメンは少なかったものと思われます。目的は子どもと親を助けること。親を助けることは子どもを助けることにもなる。虐待をする親の多くが自分自身問題を抱えていることが多いからだ。2000年代初頭には、幼稚園前の子どもが集団生活に慣れるよう、週2回2時間くらいづつ無料で預かるというサービスも行っていた。今も続いているかもしれない。もちろんおもちゃや絵本もあるし、様々なイベントも組まれる。と書いてくると、PMIっていいな、と思われるかもしれない。私もなかなかいいシステムだと思う。ただ、重要なのはシステムだけではなくてそこで実際に働いている人間たちである。フランスでは、残念ながら全くやる気を感じられない人たちもこのセンターで働いていた。当たり外れが大きいと思っていた方がいいだろう。フランスにはこんなジョークがある。「公務員と失業者の違いがわかるか?失業者は、一度は働いたことがあるってことさ。」とはいえ日本にもこんなセンターがあったらと思う。普通の人がたいていの場合、与えられた仕事を真面目にやる日本でこそ、こういったセンターが力を発揮すると思う。
<スポンサーリンク>
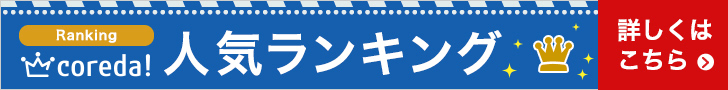
日本ではまだ親が社会に信頼されているという感じがするが、フランスで子育てしていた時はそうではなかった。学校を二日以上欠席する時や水泳に参加できない時は、必ず医師による証明が必要だった。親が休んだ方がいいと判断して休ませることができるのは一日だけだったと思う。診断書にお金がかかるということはなく、診察さえ受ければ簡単に出してくれる。そして学校は、子どもたちの出欠状況等を教育委員会に報告する義務がある。虐待されている子どもは学校を休むことが多いので、子どもがきちんと学校に来ているかどうか把握するのが重要ということなのだろう。水泳の授業で裸になれないということは、あざや傷を隠している可能性もある。日本では学校でのいじめなどが原因で長期欠席をすることも多く、事情は同じではない。が、いじめや引きこもり対策のためにも、出欠状況を把握するのは有効だと思う。学校へ行く前の子どもはどうかと言えば、PMIという保健所兼児童相談所のようなところがあり、無料で予防注射や相談が受けられる。常駐の医師はいないが、巡回で医師が訪れ、幼い子どもの定期検診を行う。無料で予防注射を受けることもできる。定期検診は義務付けられているので、検診に来なければ、何かおかしいということになるのだろう。保育士は常駐しているので、相談にのってもらうこともできる。赤ちゃんの体重計もあり、いつでも使わせてもらえる。私は子どもが小さく生まれたということもあり、最初の頃は毎日そこで子どもの体重を測っていた。(つづく)
<スポンサーリンク>
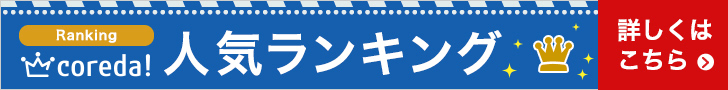
「どうして助けてあげられなかったのか。」
目黒で5歳の女の子が虐待死した事件を受け、こう思った人が多かったことだろう。
私もその一人。
児童相談所が虐待の事実を掴み、二度も施設に入っていたのに。
これまでも似たようなケースがあり、その都度なぜ救えなかったのかという声が挙がった。
児童相談所が手一杯だからなのか、それとも、法律が整備されていないからなのか。
家庭内での子どもの虐待は残念ながらどの国にもあるが、 法律による対処の仕方は国によって違う。
目黒の虐待死のようなケースであれば、フランスなら恐らく、親は強制的に子どもを取り上げられていただろう。
フランスの法律のことも私は詳しいわけではないい。
ではなぜそう思うかというと、虐待ではないのに間違いによって子どもが親から引き離されたケースが報道されたことがあるからだ。
それは極度に骨が脆くなる病気を患っていた女の子の場合で、確か複数箇所骨折していたのだと思う。
医師が虐待を疑い、通報したために親子が引き離されてしまったということだった。
後に両親は裁判を起こし、勝訴しているから、手続きに何か問題があったのかもしれない。
親から引き離されていた女の子は判決の感想を求められ、
「うちが勝って良かった。」
と答えたという。
親子を引き離すということは、一歩間違えれば別の大きな悲劇を引き起こしかねない。
しかし、何らかの法的な整備をし、一定の条件で強制的に引き離せるようにしないと、同じような事件はまた起きてしまうのではないか。
結愛ちゃんの場合二度も施設にいたというが、施設に入れる条件や親に返す条件はどのように決まっているのだろう。
児童相談所は母親に関与しないで欲しいと言われたそうだが、強制的に介入できないものなのか。
相談員が児童に会いに行って会えなかったらどうすると決まっているのだろうか。
子どもは無論国のものではなく自治体のものでもないが、親のものでもない。
子どもは誰のものでもないから。
<スポンサーリンク>
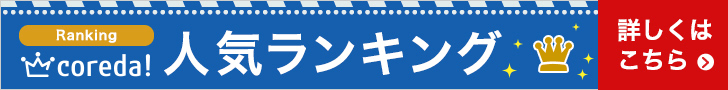

先日NHK朝イチで炭酸水の特集をやっていた。そこで私があっと驚いたのは、専門家らしきゲストの方が「炭酸水に飲み過ぎはない。」とおっしゃっていたことだ。フランスでは、医師達は炭酸水を飲み過ぎないよう注意を促すことがある。もちろん炭酸水にはいいこともたくさんある。その中の一つは、番組で紹介されていたように、食事をとりながら飲めば消化を助けるということ。炭酸水と一口で言っても、自然なガス水もあれば、フツーの水を発泡させたものもある。天然のガス水ならミネラルがとれるという利点もある。ただ、幼い子どもなどミネラルをうまく消化できない人は気をつけた方がいいだろう。我が家の子どもは、天然のガス水を飲んでいい年頃になった時、ガス水が大好きになった。フツーの水を飲むのを嫌がり、ガス水しか飲まないようになってしまったくらいである。お腹が痛くなって医者に行くと、ガス水を控えるよう言われた。こちらから「ガス水しか飲まない」と言ったわけではないのだけど。他に控えるよう言われたのは柑橘類。要するに、胃を刺激し過ぎてはいけないということだったらしい。その点で天然のガス水と人工的に発泡させた炭酸水とで違いがあるかどうか私にはわからない。が、フランスの内科医は、天然モノはダメだけど人工のはいいとは言ってなかった。自分の体調に聞くのが一番なんだと思う。
<スポンサーリンク>
ワイン専門リカーショップ 
まず、日大側の誰よりも早く誰よりもはっきりと謝罪した加害者の学生に敬意を表したいと思います。声明文を発表した日大アメフト部の部員の皆さんにも。そして、被害を受けながら加害者学生の復帰を望んでいる関西学院大の学生にも。内田監督と井上コーチがいかに言語道断であるかについては既に多くが言われているので省きます。「教育ではない」という指摘がありましたが、それどころの話ではなく、犯罪の領域に入っていると言うべきでしょう。しかし、殆どの人は内田監督のようなことをしてしまう危険はないでしょう。では、内田監督のような人が自分の上に来たら、どうでしょう。自分は井上コーチのようにはならないと断言できるでしょうか。今年から道徳教育が教科になりました。日本で特に教えなければならない道徳とは、どんな道徳でしょうか。多くの日本人が特に学ぶ必要のある道徳とは。それは、上からの命令が間違っていれば、従ってはいけないという教えではないでしょうか。自分の頭で考えなければならないと自分を律することではないでしょうか。おかしいことがあったらおかしいと言える徳ではないでしょうか。たとえ命令されても不正タックルなどするべきではなかった - 加害者となった学生の言葉はとても重いものです。指示に盲目的に従ってきてしまった - 部員たちの反省は実に的を得ていると思います。どんな組織にいても、ある日自分の上にとんでもない人が来てしまうことはあり得ます。道徳的な岐路に立たされた時、どんな行動を取るか、また取らないか。自分だったらどうするだろう・・・自分だったらどうしただろう・・・今回の事件は、私たちにとってまたとない道徳の授業となりました。後悔先に立たずと言いますが、日大の学生たちの反省を、自分の道を照らすランプとして先に掲げて行きたいと思います。










